|
「蛇含草」
★あらすじ じりじりと焦げてきそうな夏の盛りの昼下がり、横町の隠居のところへ褌(ふんどし)に麻の甚平だけの長屋の男がやって来る。
隠居の家はあちこちに涼しい工夫がしてあり長屋とは大違い。男は羨ましそうに床の間の山水や墨画を見ていると、その脇にみすぼらしい草がぶら下がっている。
男 「こんな汚い草、捨てなはらんかいな」
隠居 「これは蛇含草というて珍しいもんやで。人から聞いた話やが、山奥深くのうわばみが猟師とか旅人を呑み込んで腹が膨れた時に、この草をなめると腹の中の人間が溶けてすっきりとするというねん。まあ、魔除けにでもなるかとぶら下げてあるんや」
男 「へえ、うわばみの消化の薬でっか。話の種にするよって、少しもろうて行ってもよろしか」と、男は草を何本か甚平の紐にくくりつけた。
隠居はこの暑いのに火鉢を出して餅を焼き始める。親類の祝い事でついた餅が余ったので、餅箱一杯もらったが、夏場で足が早いので、ちょくちょく焼いているという。
餅が大好きで、大食い大会にも出るような男。隠居が焼いている間に我慢がならず、ことわりもなくパクパクと食い始めた。隠居は「親しき中にも礼儀ありという。勝手に食べだすとはあまりにも私を馬鹿にしている。行儀よくすれば、この餅みな食うたかて何も言わへんわいな」
男 「みな食いまひょか」
隠居 「これだけの餅、一つも残さずよう食うか。一つでも残しやがったら承知せんで」
男 「残しまへん。どんどん焼きなはれ」と、隠居が焼くそばからがんがん食って行く。餅を高く放り上げて”箕面の滝食い”、”お染久松夫婦食い”、”淀の川瀬の水車”なんて曲食いも披露したりする余裕だ。
焼く方も食う方も意地になって、火鉢の上には二つが残るのみだが、ついにギブアップ、「もう、あかん堪忍して、餅が鬼に見える。そっちへやって」、男は餅を詰め込み過ぎて苦しそうに下も向けず、口、鼻、目、耳からも餅が溢れ出しそうになりながら帰って行った。
家に帰った男、かみさんに奥の部屋に布団を敷いてもらって寝ようとするが苦しくて横にもなれない。苦しさ紛れに腹をさすると何かにさわった。「そうだ、蛇含草だ」と、手でむしゃむしゃと食べ始めた。
一方の隠居、さっきはこっちも意地になり過ぎたと、男の体を心配してやって来た。「この暑いのに閉め切って何をしてんのんや」と、奥の部屋の障子を開けると、餅が甚平を着て座っていた。
|
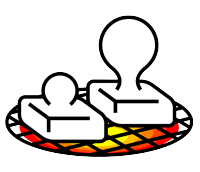 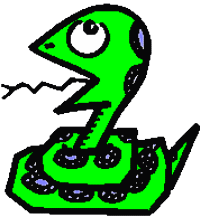 
|