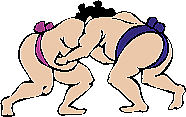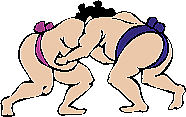★あらすじ 昔、上方では赤子の棺に砂糖桶を使うという風習があった。幼児の亡骸を砂糖桶に入れて墓地に行く男が、途中で道脇の空き地で子どもたちが相撲を取っているのに出会う。
この男、大の相撲好きで村相撲でも大関を張るほどの力自慢だ。子どもたちの相撲を見ているうちに自分も相撲を取って見たくなって、一度に二、三人の子どもを相手に相撲を取り始めた。男は強くて負けないので、子どもたちも負かそうとどんどんかかってきて、お互い夢中になっている。
そこへ通りかかったのが、新町へ遊びに行く極道者の若旦那と幇間の一八だ。わいわいガヤガヤと相撲を取っているのが面白そうで、一八は氷砂糖を詰めた桶を置いて相撲見物だ。
そのうちにいくら取っても次から次へとかかってくる子どもたちに音を上げて、男は桶を持って逃げ出すように行ってしまった。一八もあわてて桶を持って若旦那の後を追いかける。
新町のなじみの店にあがった若旦那は一八に、芸者たちの前で土産の氷砂糖の桶を開けさせる。すると中には赤子の死体が入っている。芸妓たちは、「キャ~」と逃げ出したり、へどを吐いたり、腰を抜かしてへたり込んだりして大騒ぎ。
若旦那 「おい、一八、何やこれ!こんなん座興にもならへんで」
一八 「へぇ、すんまへん。相撲を取っていた男が取り違ったようで」
若旦那 「いまさらなに言うねんや。氷砂糖思てこの赤子の頭かじって見いや」
一八 「そんな無茶な。気色悪いし、罰(ばち)があたりまんやがな」
若旦那 「罰があたる?そんなことありゃせん。おれなんぞずっと親の脛(すね)かじっとる」
|